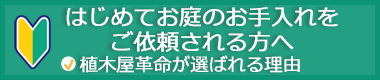うだるような夏、道の駅や花屋、軒先で見かける鮮やかなホオズキのオレンジ色に、日本の夏の訪れを感じます。やがて迎えるお盆は、ご先祖様が帰ってくる大切な時間です。
この記事では、お盆に欠かせないホオズキの意味や、お供え物の準備、家族で楽しめる精霊馬・精霊牛の手作り方法をご紹介します。
忙しい日々のなかでも、故人を偲び、家族のつながりを感じるお盆に、少し心を向けてみませんか?
1.「お盆」とは?お盆のお供えの始まり
2.地域で異なるお盆の時期と風習とは?
3.お盆にホオズキを飾る理由とは?
4.お盆のお供え物と準備のポイント
5.お盆にナスとキュウリを供える理由とは?
6.精霊馬・精霊牛の作り方
7.お盆のお供え物の処分方法
8.まとめ
1.「お盆」とは?お盆のお供えの始まり

お盆は、正式には「盂蘭盆会(うらぼんえ)」と呼ばれ、仏教のご先祖様供養の行事に由来しています。
日本では古くから祖先を敬う信仰と結びつき、独自の文化として受け継がれてきました。
この期間、ご先祖様が年に一度家に戻ってくるとされ、私たちはキュウリやナスで作った精霊馬(しょうりょううま)・精霊牛(しょうりょううし)に願いを込めて、迷うことなく無事に帰ってこられるようお迎えします。
お供え物には、ご先祖様への感謝の気持ちや、今を生きる私たちからの近況報告が込められており、
目には見えなくても、心の中で確かなつながりを感じられる、大切なひとときとなります。
2. 地域で異なるお盆の時期と風習とは?

お盆の期間は地域によって異なりますが、一般的には8月13日から16日頃に行われることが多く、「お盆休み」として広く知られています。一方で、旧暦に基づいて行う地域や、7月にお盆を迎える地域もあります。
たとえば東京では、新暦に合わせて7月にお盆を行うのが主流です。そのため、家族の中に東京出身の方がいる場合は、他県に住んでいてもその習慣を受け継ぐことがあります。
筆者自身も幼少期は静岡で過ごしていましたが、祖母が東京出身だったため、7月13日〜16日のお盆を行っていました。近隣の家庭とは時期が異なっていましたが、それぞれの土地や家族に根ざした風習があることを実感しました。
3.お盆にホオズキを飾る理由とは?

お盆の準備でよく目にするもののひとつに、鮮やかなオレンジ色が印象的な「ホオズキ」があります。
ふっくらと膨らんだ袋状の形と、提灯のような可愛らしい姿から「鬼灯(ほおずき)」という漢字が使われ、亡くなった方々を導く灯りとしての意味が込められています。
ホオズキはお盆の時期にちょうど色づくため、季節を象徴する植物としても親しまれています。
ご先祖様が迷うことなくあの世とこの世を行き来できるよう、足元を照らす「提灯」の役割を果たしているといわれています。
また、ホオズキの空洞の中には精霊が宿るともされ、その神秘的な存在感も大切にされています。
仏壇の横や玄関先に飾られたホオズキを見ると、「ああ、今年もお盆の季節が来たな」と感じる方も多いのではないでしょうか。
ホオズキは単なる飾りではなく、ご先祖様への歓迎と敬意を込めた、大切なお供え物のひとつなのです。
4.お盆のお供え物と準備のポイント

ご先祖様をお迎えするにあたり、心を込めた「お盆のお供え物」は欠かせない大切な準備です。
故人が生前好んだ食べ物やお菓子、旬の野菜や果物、水やお酒など、想いを込めて選んだ品々をお供えします。
地域によっては、お盆菓子や団子など、特別なお供え物を用意することもあります。
また、お供え物に加えて、線香の香りは場を清め、ろうそくの灯りは暗闇を照らす道しるべとなり、ご先祖様が迷わず帰ってこられるよう導いてくれます。
お盆準備のポイント
- 仏壇やお墓の清掃:清らかな環境でご先祖様をお迎えしましょう。
- 迎え火・送り火:地域によっては玄関先などで火を焚き、来訪と帰路を見送ります。
- 提灯の準備:ホオズキや絵柄付きの盆提灯で、あたたかく迎える雰囲気を演出します。
- お供え物の用意:故人の好物や季節の食材を丁寧に準備しましょう。
ご先祖様が安心して戻ってこられ、気持ちよく過ごしていただけるように――
家族みんなで協力して進めるお盆の準備は、心をつなぐ大切なひとときとなります。
5.お盆にナスとキュウリを供える理由とは?

お盆の時期になると、仏壇や盆棚にナスとキュウリが供えられているのをよく見かけます。
「精霊馬(しょうりょううま)」と「精霊牛(しょうりょううし)」と呼ばれます。
これらは単なる飾りではなく、ご先祖様への深い願いと、日本の豊かな風習が込められた大切なお供え物です。
精霊馬と精霊牛の意味と由来
- キュウリの馬:ご先祖様が早く私たちの元へ戻ってこられるように、という願いが込められています。
- ナスの牛:帰りはたくさんのお供え物を載せて、ゆっくりとあの世へ戻っていただきたいという祈りが込められています。
この風習は江戸時代頃から広まり、今でも多くの家庭で受け継がれています。
一般的には、お盆の入り(8月13日)夕方にご先祖様をお迎えするために、盆棚や仏壇の近くに顔を家の方に向けて供えます。
そして、お盆の送り(8月16日)には、顔を家の外に向けて飾り、見送りをします。
6.精霊馬・精霊牛の作り方

お盆の準備の中でも、特に心が温まる手作りアイテム「精霊馬(しょうりょううま)」と「精霊牛(しょうりょううし)」を子どもと一緒に作ってみました。
【準備するもの】
- きゅうり:1本(馬用)
- ナス:1本(牛用)
- 割り箸または竹串:各4本(足用)
【作り方】
1. きゅうり(精霊馬)を作る
きゅうりを横に置き、割り箸や竹串を胴体の四隅にしっかり差し込んで足を作ります。
ご先祖様が少しでも早く家に帰ってこられるよう、足の速い馬に見立てています。
2. ナス(精霊牛)を作る
ナスも同様に、四隅に割り箸や竹串を差し込んで足を作ります。
お供え物をたくさん積んで、ゆっくりとあの世へ戻っていただく牛に見立てられています。
※ 割り箸の位置によってはバランスが崩れることもありますが、それも手作りならではの味わいです。
調整しながら、楽しんで仕上げてみてください。

7.お盆のお供え物の処分方法
お盆が終わったら、ナスやキュウリ、ホオズキなどのお供え物は、感謝の気持ちを込めて丁寧に処分しましょう。
精霊馬や精霊牛に使ったナスやキュウリは、ご先祖様の乗り物とされるため食用にはせず、衛生面からも処分するのが一般的です。
かつては川に流したり土に埋めたりしていましたが、現在は自治体のルールに従い、白い紙に包んで捨てる、庭に埋めるなどの方法も選ばれています。
また、使わなかった野菜は料理に活用したり、ホオズキは乾燥させて秋の飾りにするなど、再利用する工夫も可能です。
自然の恵みに感謝し、心を込めて見送りましょう。
8. まとめ

お盆は、古くから日本に根付いた、ご先祖様への感謝と敬意を表す美しい風習です。忙しい日々の中で、家族のつながりや命の大切さに気づかせてくれる貴重な機会でもあります。
筆者も祖父の好物だったビールと落花生を供えながら、「今年もきっと来てくれるな」と自然に思えました。
この夏は、手作りの精霊馬・精霊牛とともに、お供え物を用意してご先祖様を迎えてみませんか。
| あわせて読みたい記事 |
|---|
| お墓のお手入れをして気持ちを伝えよう |
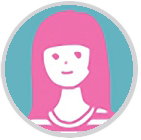
冨宇加ナターシャ |植木屋革命 WEBマーケティング・編集担当 植木屋革命のWEBコンテンツ全般を担当。これまでに執筆した記事は100本を超えます。 庭いじり初心者の方にもわかりやすく、気軽に楽しめるガーデニング情報を発信中。季節ごとの植木の手入れのコツや、ちょっと珍しい野草の話題など、暮らしに寄り添う“緑のヒント”をお届けしています。 |